コラム
情報システム導入のROIについて
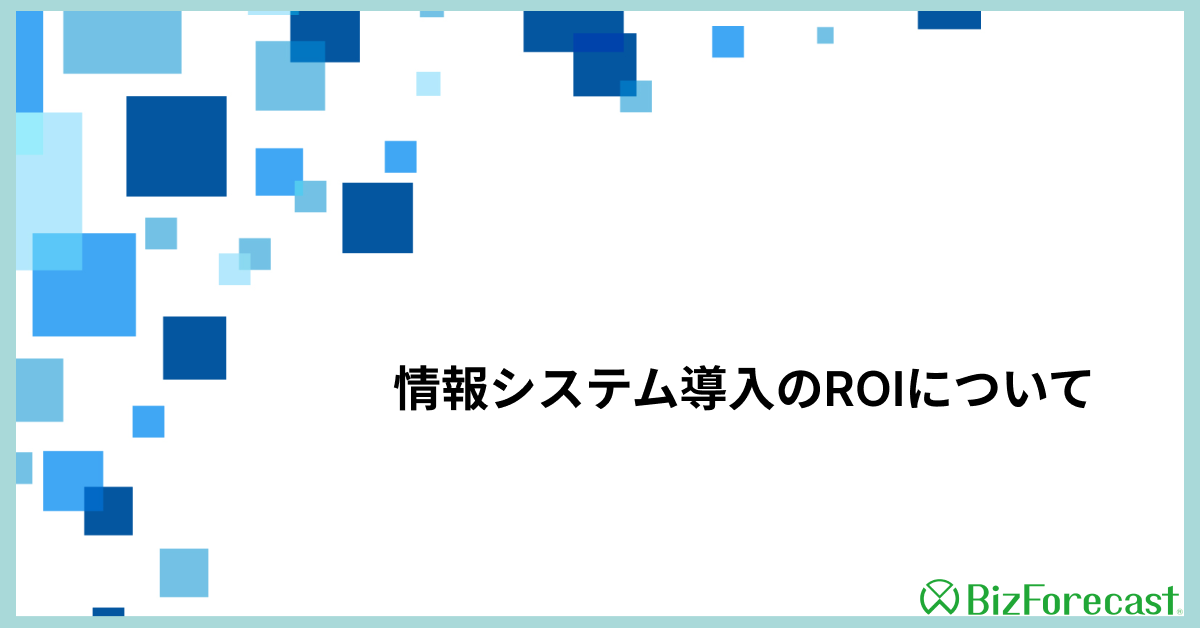
情報システムを構築、導入する場合にその投資が見合うものかを具体的に求められることが多いかと思います。
特に社内手続きとして定量的な効果を明示して稟議を回すことを求められことが多くみられます。
場合によっては、経営者から「それで何人分の工数を減らせるのか」と言われることもあるのではないでしょうか。
01. 情報システムのROI
この投下する金額とその効果は、「情報システムのROI (Return on Investments:投下資本利益率)」として表されます。
ROIは投資した金額に対してどれだけ利益を生み出したか表わす指標で、詳細は割愛しますが、「利益」に関しては目的や状況に合わせた様々な利益が使われます。
一般的にROI の定量面の効果として作業の時間削減や売上の増大があげられます。
時間の削減に関しては対象となる業務を細分化して現在の業務時間を算出し、新たにシステムを導入した場合に削減される時間との差異から削減できる人件費を算出するとともに、システム導入によるその他の削減可能な費用を合算し、多少手塩を加えて「効果」とするようなことが行われます。
これはいわばプラスの効果ですが、業務を効率化することによってその業務の周辺業務や関連する間接業務にも影響(負の効果)をもたらすことがあります。
そのようなマイナス分は含められることが少ないでしょうし、もうひとつの売上の増大に関しても、もちろん前提をおきながら「ざっくり」何割増しというようなことが現実ではないでしょうか。経営者にしても必要性は十分理解するものの、「眉唾な数字」と認識されている場合もあるのではないでしょうか。
大きな投資の決断に対する拠り所となるものが欲しいということだと思います。
02. システム導入における効果測定
ところで実際はこのような「定量的な効果」なんて「わからない」というのが多くの関係者の皆さまの本心ではないでしょうか。わからないながらも他社の事例があればそれも考慮にいれて、「不相応な投資による情報システムではない」ということを検討し合意をとり、結果として残すということではないでしょうか。
それ(だけ)でよいのでしょうか?
経営判断にあたっては、どうしても定性面よりも具体的に数値で表された定量面に焦点があたりやすく、説得力もあるかもしれません。
しかし、システム導入の仕組み化によって、作業ミス等のリスク低減が図れ、手作業よりも正確性が担保されます。
また、情報システムを導入することはシステムの担当者だけではなく、業務の担当者も関わるのが一般的ですので、それによって情報や情報技術のリテラシーが底上げされ、向上につなげることができます。特に会社の基幹業務にかかわるシステムを導入するような場合は、将来的に会社を背負って立つようなひとに関わってもらうことで俯瞰的に組織や業務をみて捉えられるようになり、プロジェクトを運営するちからもつけることにつながり、経営者、管理者の育成にもなります。
そのような中長期的にみた定性的な効果が重要になるものと思います。
前述の情報システムによって売上を拡大させるような仕組みをつくることは、一般的に効率的に業務改善するといったレベルよりも、乗り越えなければならいその壁は高いと考えられます。ただこのシステム導入によって顧客や従業員の満足度を上げていくような定性的な効果が売上増大に結び付くようになるかもしれません。
経営者にも定性効果の重要性を理解してもらう努力をして、目安としての定量数値だけではなく、特定の従業員や部門の育成、顧客との関係強化等、
具体的・定性的な効果を明示しながら情報システムの導入や構築を進める必要があるものと考えます。
(上記はプライマル社としての考えではなく、あくまでコラム執筆担当の個人的な考えです)
